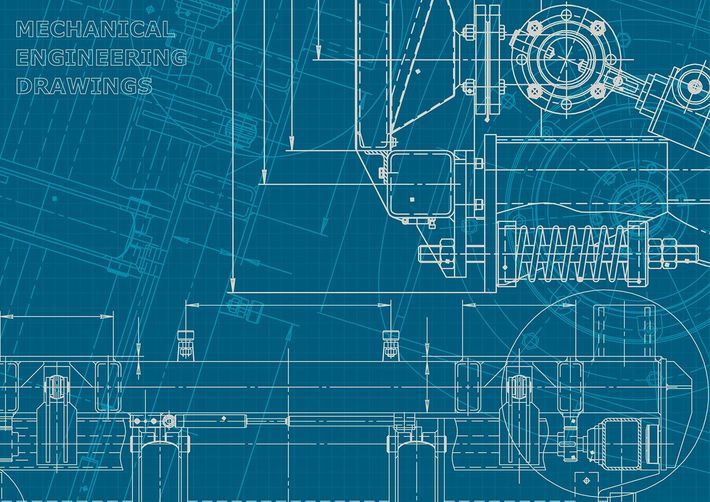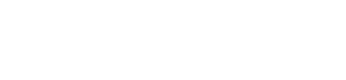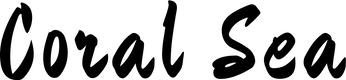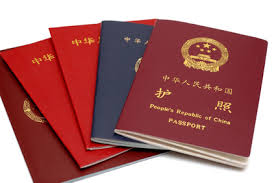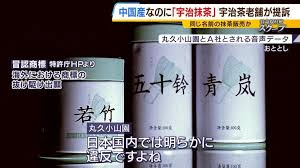中国人技術者が日本から
スマート農業情報を流出

先日、中国国内で日本の大手企業アステラス製薬の社員である50代日本人男性がスパイ活動を行った疑いがあるとして、中国国家安全局によって、反スパイ法違反容疑で帰国直前に拘束された。
そして、すぐに林芳正外相が訪中し、本件を含む中国国内での日本人の拘束に抗議して早期解放を強く申し入れたが、中国からは「法律に基づき処理する」との回答を得たのみであり、早期釈放に暗雲が立ち込めている。
このように、中国によって不透明かつ曖昧もしくは恣意(しい)的に法が運用され、多くの日本人が拘束されている。彼らは極めて厳しい環境下に置かれていると想像されるが、ご本人とそのご家族・関係者を思うと憤りが隠せない。また、既に釈放され帰国された方々も同様に非常に苦しく厳しい時間であっただろう。
このような状況下で、今度は国内電子機器メーカーに勤務していた中国人男性技術者が昨年、スマート農業の情報を日本から不正に持ち出したとして、警察当局が不正競争防止法違反容疑で捜査していたことが報じられた。
報道によれば、同中国人男性は、中国共産党員かつ中国人民解放軍と接点があり、SNSを通じて、中国にある企業の知人2人に情報を送信していたという。
この男性は別の事件で浮上し、捜査側から国内電子機器メーカーに連絡が入り発覚。その中で事情聴取などするなどの捜査を進めていたということである。
この中国人男性は既に出国済みであり、今後の捜査は極めて難しく、中国に渡った技術はもう日本に戻ってこない。捜査機関も当然尽力したと思われ、極めて無念の思いであろう。
正当に入社した社員が
情報流出に関与するリスク
今回の国内電子機器メーカーの事件では、どのように情報が持ち出しされたのか。
本件の中国人技術者は、クラウド上で管理された「スマート農業」の情報について、社内でも正当にアクセスする権利を持っており、平素から問題なく勤務していたと思われる。
実は、スパイ事件というと、ロシアによるスパイ事件を例に、人的ルートを通じて日本人エージェントを使い、不正に情報を窃取するという方法がよく思い浮かべられる。例えば、ロシア対外情報庁(SVR)の「ラインX」によるソフトバンク事件だ。同事件では、ラインXの一員であるロシア通商代表部の外交官がソフトバンク元社員に接触し、同社の営業秘密である機密情報を不正に取得した。
だが、実態はそればかりではない。
本件の中国人技術者は、国内電子機器メーカーに技術者として正当に入社し、正当な業務の中で、正当なアクセス権を持って日頃から勤勉に働いていた。ところが、実は国家の指揮命令下にあり、アンダーでは技術情報を持ち出し、国外に送信していた。
入社当初から中国共産党の影響下にあるケースだけではなく、入社後に影響下に入るパターンもある。
過去の事件では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)などの約200の団体・組織が2016年6月から大規模なサイバー攻撃を受け、その一連のサイバー攻撃に使用された日本国内のレンタルサーバーを偽名で契約・使用していたとして、2021年12月、捜査機関が2人の中国人を私電磁的記録不正作出・同供用容疑で書類送検した。
この書類送検された中国人の一人は中国人の元留学生「王建彬」容疑者であり、彼はレンタルサーバーの契約を人民解放軍のサイバー攻撃部隊「61419部隊(第3部技術偵察第4局)」所属の軍人の女から頼まれたという。
なんと、王容疑者が以前勤めていた中国国営企業の元上司が王容疑者とその女をつないだという。
この事件の恐ろしいところは、善意の中国人男性が、中国共産党に利用されたということである。
合併会社を設立して
合法的に情報を流出
もちろん、中国共産党の指揮命令下にある中国人技術者が当初からその身分を隠して企業に入社する場合もある。
さらに、公安調査庁のHPにも掲載されているが、合法的な経済活動による技術流出も当然存在する。
例えば、合弁会社の設立である。
中国企業との合弁では、日本企業が最新の技術は合弁先に共有しないという立場を取る場合が多い。
しかし、日本企業のガバナンスが弱いため、現地への技術指導を目的に日本人社員が機微情報(図面等)を持ち出してしまい、その結果、現地に技術情報が共有されてしまい、合弁解消後も技術情報は現地に残ったままという事例もある。
米国が世界に警鐘を鳴らしているように、中国による諜報活動・技術流出は違法な手法のみではない。
中国の千粒の砂戦略(※1)を例に、悪意・善意問わずビジネスパーソンや留学生が日本で知見を蓄えて帰国する手法(こうした人々は「海亀族」といわれる)や、調達などの合法的な経済活動によって、日本の知的財産が侵食されている点には極めて留意しなければならない。
また、中国に進出する企業では、中国国産化政策(現地設計・現地生産が求められ、拒否すれば市場から締め出されるような政策)や在中国欧州商工会議所が2021年1月に公表した報告書が示している半強制的な技術移転に留意しなければならない。
※1 千粒の砂戦略:ロシアのようにスパイによる典型的な諜報活動ではなく、人海戦術のごとく、ビジネスパーソン・留学生・研究者など多種多様なチャネルを使用し、情報を砂浜の砂をかき集めるように、情報が断片的であろうとも広大に収集する戦略。
スマート農業の情報が
なぜ中国に狙われたのか
今回の国内電子機器メーカーの事件では、ビニールハウスの室温や土壌の水分量等を最適に保つ機器のプログラムに関する情報が不正に持ち出されたという。
中国では、かねて自国の農業近代化を掲げているが、中国政府が発表している外商投資奨励産業目録(外国投資家による投資の奨励および誘致に関連する特定の分野、地区等が明記されたリスト)の最初には農業関連が掲げられており、その中には、以下のように今回の事件にひも付く内容もある。
一.農業、林業、牧畜業および漁業
20.スマート農業(ソフトウェア技術および設備の統合活用、農業生産・経営管理のデジタル改造)
(中華人民共和国商務部「外商投資奨励産業目録2022」より一部抜粋、翻訳JETRO)
企業関係者などは、ぜひ参考として当目録に目を通していただき、自社に関連する技術・情報・ノウハウがないか確認していただきたい。
経済安全保障における
スパイ防止法の必要性
経済安全保障という言葉がトレンドになって以降、中国による技術窃取の問題がクローズアップされてきた。日本においても、これまでも存在していたリスクが正しく捉えられ始め、社会の認知は広まってきたといえる。
一方で、前述のように事件化や表面化した諜報事件・技術流出事件は、ほんの氷山の一角であると断言できる。
このような極めて厳しい状況下にもかかわらず、我が国にはスパイ防止法がなく、スパイ活動を取り締まる法的根拠がないため、捜査機関としては、法定刑がさほど重くない窃盗として、もしくは不正競争防止法等の適用を駆使しながら何とか対応している。
そこで、検討されるべきが、スパイ防止法である。
スパイ防止法は、中国の反スパイ法を反面教師に、その定義が決して曖昧であってはならず、恣意的な運用の余地を一切なくさなければならない。
また、日本弁護士連合会による1985年の「『国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案』に反対する決議」(LINK)にもあるように、スパイ行為自体が、日々の生活に非常に密接であり、スパイ行為の処罰が基本的人権を侵害する恐れもあるため、法案内容の検討には十分かつ慎重な議論がなされる必要がある。
しかし、現在、世界は変動期にある。今一度、日本のカウンターインテリジェンス(防諜活動)を考え、スパイ防止法の本格的な検討をするときが来たのではないだろか。
(日本カウンターインテリジェンス協会代表理事 稲村 悠)