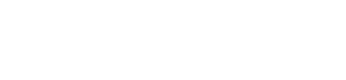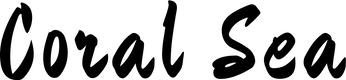『セーラームーン』『NARUTO』『鬼滅の刃』『ポケモン』などの日本のアニメは、アジアのみならず欧米でも大人気だ。「日本に来て感動したこと」としては「電車が時間通りにくる」「街が清潔」などが挙げられることも多い。 そうして日本を好きになってくれた若者が日本の研究をするとは、なんと嬉しい話だろう。しかしベルギーに暮らすジャーナリストの栗田路子さんが参加した「日本研究カンファレンス」では、想像を超えた「研究結果」が発表されていた――。以下、栗田さんが見聞きしたことを寄稿いただいた。
日本語堪能な研究者たちが1000人以上
今年夏、私の住むベルギーの古都ゲントの大学に、まるで日本人かと耳を疑うほど日本語が堪能な研究者たちが、世界中から1000人以上も集まっていた。コロナ禍明けて4年ぶりに、対面で開催された『ヨーロッパ日本研究協会(EAJS)』が開催するカンファレンスでのことだ。 私は30年来、多くの日本研究の学者たちに出逢ってきたが、彼らの日本理解の幅と奥深さ、そして日本への愛にはいつも仰天してしまう。何度も何度も日本に足を運び、合計すると何年も日本に住み、平均的日本人以上かと思うほど日本の新聞や雑誌に毎日のように触れて、「日本の家族」と呼ぶほどの近しい人々や友人のネットワークをしっかり培っている。 EAJSは1973年設立。かつて、日本研究(Japanese Studies)といえば、歴史や文学、美術や伝統芸能というのが研究テーマの中心だった。学者には、純文学者や芸術家タイプが多かった。その後、2桁経済成長期には、日本式経営が持てはやされて、経営学や組織論などのテーマが増えた。バブルがはじけた後には、世界中で、日本アニメが脚光を浴び、書店に「MANGA」が並び、世界の人々が日本にのめり込むきっかけはがらりと変貌した。 ベルギーでも、『ポケモン』や『NARUTO』はもちろん、最近では『鬼滅の刃』(ただし『Demon Slayer』として)なども大人気で、コスプレ・イベントやマンガの専門店ばかりか、キミョウな日本語らしき看板を掲げたグッズショップまである。このようにして日本が好きになった若者が増えている今、日本研究でも「ポップカルチャー」に焦点が当てられているのかと私は予想していた。
日本の今を見透かしたような社会問題がずらりと
ところがどうだろう。200以上ものワークショップのテーマを一覧して、思わずのけぞってしまった。「安倍元首相暗殺と旧統一教会」「差別的言動を煽るメディア」「非正規移民と入管問題」「低迷する若者の政治参加とシルバー民主主義」など、まるで、日本のリベラルメディアを見ているかと錯覚するほどだったからだ。 イマドキの若手学者たちは、日本の社会現象をリアルタイムで見ている! 昔ながらの俳句や能狂言、かつて一世を風靡したKanbanやJust-in-time、アニメやコスプレばかりをほめそやしているわけじゃないんだ、と。 一般的なヨーロッパ人に聞けば、今でも、「日本人は優しくて寛容」「日本は豊かなハイテク立国」と大褒めし、「いいね」イメージに引きずられている人が多いのは事実だ。でも、私は悟った。「やばい! ここにいる最先端の若手研究者は、日本の現状を、すっかり見破っている!」と。 若手を指導する立場にある欧州在住の中堅学者に聞けば、日本研究において「社会問題」が研究テーマに急増したのは、「2010年代頃」からだという。靖国や慰安婦、在特会などが国外メディアでも伝えられると、大学院の学生たちは、差別やヘイト、分断や右傾化などに関心を持ち始めた。彼らの中では、ニッポンカイギとか、モリカケサクラとか、ヘノコとか、そんな語彙が普通に飛び交う。 20~30代の若手は、子どもの頃から、日本のマンガ、アニメ、ゲーム、コスプレなどのポップカルチャーに惹かれて日本研究の世界に入った「ミレニアル世代」だ。「日本大好き」から日本語を学び、日本社会に浸るために留学し、日本人の友だちをたくさん作ったという学生も多かったようだ。彼らは、「日本っていいね」の真っただ中にいたのだ。 でも、飛び込んだ「大好きな」日本で、在特会が街を練り歩いていたのに遭遇した人も少なくなかった。SNS上にネトウヨ・パヨクの差別言葉が溢れ、恋い焦がれていた日本像ががらがらと崩れていったという人もいる。日本への熱い思いから覚めて、離れていく大学院生や研究仲間の後ろ姿もたくさん見送ったという。 それでも、今もなお、日本をテーマに研究する彼らの心の内を聞いてみた。
東日本大震災に遭遇したウクライナ人女性
1)ロシアによる偽情報に操作される日本人のウクライナ感情を研究するオレナ ———- ウクライナ人としてチェルノブイリを身近に育ったオレナが日本に留学したのは2010年。幼い頃から、母 の書棚にあった松尾芭蕉や石川啄木に親しみ、キーウ大学では日本文学を専攻。日本研究で博士を目指すためにウクライナからドイツに移住した。日本で学びたい! ようやく夢かなって筑波大学大学院に留学した翌年3月、彼女はなんと東日本大震災に遭い、福島第一原発事故を経験してしまう。彼女が住んでいた茨城県は福島県南部に隣接。つくば市でも震度6弱とかなりの揺れだった。地震がほとんどないヨーロッパ育ちの彼女には恐怖の体験だった。 これほどの大地震と原発事故に遭っても、落ち着いて互いをいたわりながら生きる日本人を間近に見て感動し、日本のニュースや政府の指示をすっかり信じて従った。同時に、「チェルノブイリと福島の2度の原発重大事故を経験した数少ない学者」として、日本がいかにして事故を転機に脱原発していくか、メディアはその過程にどんな役割を果たすかを博士論文の研究テーマにしようと考えた。 欧州経由でメルトダウンが起こっているという情報や映像が届いたが、日本でそれが知らされたのはずっと後になってのことだった。「日本国内にいても原発事故の詳しい情報が入手できるとは限らない」と悟った。むしろ、ドイツから日本の情報やメディアを追って大局的に見つめた方がよいのではないかと考えて欧州に戻った。ドイツでは、福島での原発事故をきっかけに、「脱原発」が決断された。日本でも同じように、一旦停止した全国の原発は二度と稼働されずに、再エネ転換が加速すると信じた。 ところが、当初のショック状態から覚めると、日本社会は変革の気運を日増しに失っていったようにしか見えなかった。メディアは「日本には(化石)資源が乏しいし、再生エネは高くつくから、原発やむなし」との論調が増え、日本の友人知人はいつしか「ショウガナイ」を繰り返すようになっていた。
ロシアのウクライナ侵攻で日本のSNSを見ると…
日本からもどって10年余りが過ぎた2022年2月末、博士論文のテーマを変える出来事が起きた。突然、ロシアが祖国ウクライナに侵攻したのだ。オレナは、日本語の世界で、「#ウクライナ」とついたツイートやウクライナ侵攻に関連するSNSの収集と解析に着手した。意味上の分類と数量的な解析、発信元はどこの誰かといった分析だ。ウクライナ語、日本語、ドイツ語以外に、ロシア語や英語も堪能なオレナは、ロシア当局が、世界各地で様々な言語で拡散し始めたSNSの情報をそのまま理解することができる。 日本人向けには、ロシア当局は日本語で情報拡散しているが、実際は、他の言語とほぼ同じ内容で同じ論旨であることがすぐにわかった。当初、ウクライナに同情的だった日本語のSNS空間では、ロシアによる情報拡散が進むにつれて、反ウクライナ・親ロシア的な内容の投稿が増えていく様子が見てとれたという。 メインストリームのメディアなら、情報工作が直接影響することは少ないだろう。だが、そもそも日本のジャーナリズムは現地ウクライナやウクライナ政府からの一次情報に乏しい。疑ってみることに慣れていない日本人は、それらしい体裁をとっていれば、SNSによる戦略的情報誘導にとても弱いように見えた。 また、オレナの研究によれば、ロシア当局が拡散する親ロシア・プロパガンダは、ここ10年ほどの間に勃興した新右翼メディアや論客による陰謀論的な主張と内容的に驚くほど重なっているのだという。ロシアの偽情報や陰謀論が、いかに一部の政治家たちに強く影響し、利用されているのかを検証することも、オレナの博士論文のテーマの一部なのだというから、驚いた。たとえば、最近、渡航中止勧告の出ているロシアを訪問してニュースとなった鈴木宗男氏(当時、維新の会)は、「アメリカの狙いはウクライナでの戦闘をわざと長引かせることで西側の武器産業を潤わせること」などの言説を発信していた。これはかねてからSNSでロシア当局が拡散してきた内容とぴたりと重なっているのだという。
日本文化や空手に魅了され…
母の書棚にあった日本文学から日本に魅了されていったオレナ。同時にKARATEを通して日本精神に触れた。オレナはその後、ミレニアル世代の日本ファンらしく、マンガやアニメなどのポップカルチャーにも親しみ、1年間の留学以来、何度か訪日するうちに、今では、日本の陶芸にハマっているという。「好きな陶芸家は?」と聞くと、濱田庄司、伊勢崎淳(崎は本来はたつさき)、橋本忍、安部太一、小川綾、田村文宏……と私の知らない名前をすらすらとあげた。現在は博士論文の仕上げに追われている。 「日本は大好き。でも、日本のような豊かで平和な国に生きているとそれに慣れてしまって、社会をよくしたい! みたいなチャレンジ意欲がなくなってしまうのではないかと思う。女性の社会的地位の向上とか、様々な少数派の人権問題とか、できることは山ほどあるのに……」とオレナはため息交じりで話してくれた。
栗田 路子 現代ビジネス