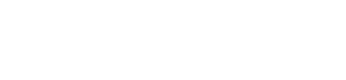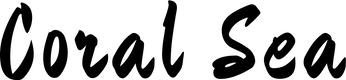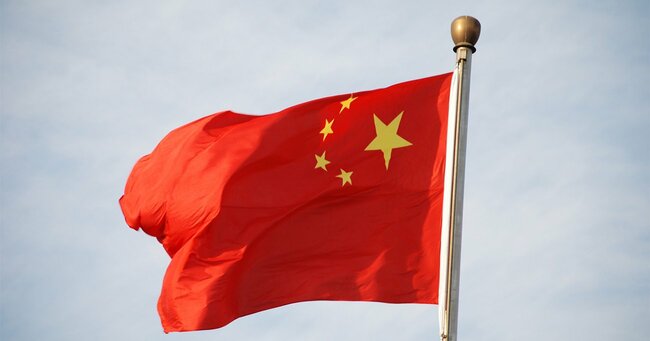
垂秀夫(たるみ・ひでお)駐中国日本大使は4日、近く離任するのを前に北京の日本大使館で記者会見した。中国当局に反スパイ法違反容疑で拘束されたアステラス製薬の日本人男性社員が解放されていない状況について、「私個人として極めてじくじたる思いだ」と述べた。7月の改正反スパイ法施行に合わせて米国務省は中国本土への渡航警戒レベルを4段階中2番目に高い「3」とした。しかし、日本の危険レベルは「ゼロ」だ。こうした状況を疑問視した松原仁・元拉致問題担当相(衆院議員、無所属)が質問主意書を提出したが、政府の答弁書は「ゼロ回答」だった。これで日本国民の安全は守られるのか。 ◇ 3年間の任務を終え6日に帰国する垂氏は、11月下旬に大使として初めて男性社員と領事面会した。会見で「任期中に助けることができなかったことについておわびを伝える必要があり、それが人の道であると感じた」と述べた。日中関係について「立場の相違や摩擦があるのは正常なことで、それを恐れる必要はない」と指摘。「摩擦や意見の相違があればあるほど、日中関係の意思疎通は強化されなければならない」と訴えた。 中国は7月に改正反スパイ法を施行し、従来の「国家機密」の提供に加え、「国家の安全や利益に関わる文書やデータ、資料、物品」の提供、窃取、買い集めなども取り締まり対象となった。「国家の安全」の定義もあいまいで、各国は中国に滞在する国民が恣意(しい)的に摘発されることへの懸念を強めている。 米国務省は6月末から、中国本土と香港、マカオの渡航警戒レベルを「3(渡航の再検討)」に引き上げた。「現地法の恣意的な執行と不法拘禁のリスク」を理由とした。従来のレベルは「2(注意の強化)」だった。 一方、日本の外務省の「危険情報」では、中国に関して《国家安全部門に長期間の拘束を余儀なくされるのみならず、裁判で有罪となれば懲役などの刑罰を科されるおそれがある》と警告しているが、中国の主要部は4段階の危険レベルに含まれていない。 日米で危険情報が大きくかけ離れていることに松原氏は憤りを隠さない。 「過去に日本で中国批判を展開してきた人が渡航すれば『見せしめ』のために摘発されたり、ビジネス取引上のやり取りでも一方的に『重要機密扱い』にされる可能性も否定できない。中国に迎合するのは疑問で、外務省の親中派が隠然たる力を持っているのではないかと疑いたくもなる。日本は経済制裁もする力もなく、中国国内の人権侵害に対する制裁にも踏み切れない。せめて危険レベルは上げるべきだ」と喝破する。 松原氏は11月、内閣に文書で質問する「質問主意書」を提出、「日本国民への不当な拘束の危険は存在すると考えるか」「日米両政府で中国危険情報の評価が著しく異なるのは、いかなる理由によるものと考えるか」など4項目をただした。 政府は今月1日付の答弁書で「米国国務省の見解を前提としたもの又は同国政府の見解について問うものであるため、政府としてお答えする立場にない」とした。そして外務省の危険情報の記載を引用し、「同国に渡航・滞在する邦人に対して注意喚起を行っているところである」と回答するに留めた。 松原氏は回答を受けて、「邦人を大事にしていない。警戒心がなさすぎる。注意喚起のコメントを出しながら、なぜ危険レベルを上げられないのか疑問が残る。制裁できないのなら、せめて警告を発するべきだ。中国への忖度(そんたく)を続けると国際社会から孤立しかねない」と強調した。 アステラス製薬社員の男性を含め、2015年以降、少なくとも17人の日本人が拘束されたとみられる。 東京大学の阿古智子教授(現代中国研究)は「日本の大学は外務省の基準で留学の方針を考えることが多く、教え子を持つ身としても懸念を抱く。詳細な注意事項を羅列すると、安全保障上の機微に触れる可能性もあり、難しい面もあるのかもしれないが、本来は警戒レベルを上げる必要があるのではないか。中国に実際の拘束や逮捕事例などを提示して折衝するのも手だ。独自の調査や判断を下せないのは日本の根本的な問題だ」と指摘した。夕刊フジ